2017/04/25
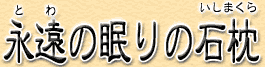

石でできた冷たい枕。これ、古代人の水枕?いやいや、実は死者のための枕で、豪族(権力者)が永遠の眠りにつくため、古墳に埋められた副葬品なんだ。
昭和62年、当時の鹿島町が文化財に指定。佐田の 国神神社に奉納されていたらしいんだけど、盗難に遭ってはいけないと、現在は鹿嶋市教育委員会が管理しているんだ。同神社の 祠のある場所は周囲より小高く盛り上がっていて、古墳(円墳)があったみたい。
滑石という加工しやすい石ででき、よく見るとのみで削った後が残っている。大きさは縦26センチ、横27,5センチ厚さ10センチ、重さは約12キロ。頭がおさまるように真ん中がくぼんでいる。 石の少ない千葉や茨城の古墳から多く出土しているのは、豪族たちが“最後のぜいたく”として使ったせいかもしれないネ。鹿嶋市内での確認はこれまでたった2例でもう一つは鹿島神宮が所蔵しているんだ。
(写真:ノミで削られた跡が残る石枕。くぼんだ部分に頭部が納まる)
カテゴリ:埋文ニュース-市内遺跡めぐり
|